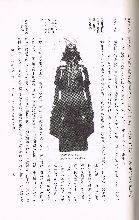岩国市史
戦国時代〜関が原直前
岩国徴古館 岩国市史編纂所 昭和32年(1957年) 編集
第一部(A) 岩国移封前における吉川氏史概観
第一編 駿河・安芸両吉川時代諸豪の活動
第三章 元春の芸・備・防・長・石・雲六ヵ国における活動
第四章 元春の四国・九州方面における活動と山口動乱の鎮定
第五章 尼子勝久の出雲乱入と元春の雲・伯・因・但諸国の経略
32頁
操作法: ページ縮小図を押すと拡大ページになり両端を押すと頁めくりです。拡大後、枠外周辺を押すと閉じます。
-
第三章 元春の芸・備・防・長・石・雲六ヵ国における活動
第一節 元春の芸備両国における活動
・1548年、毛利元就の軍に合流して山名理興の守備する神辺城を攻撃した。固屋口で山名理興の軍と交戦して撃退し大内義隆から感状を受領した

単ページ
-
・1554年、陶晴賢は大内義隆を殺害して大内義長を擁立した。毛利元就は陶晴賢と絶縁状態になり、陶晴賢側の城を攻めた。
安芸国佐伯郡廿日市の西方にある折敷畑合戦では数千の敵兵を包囲して奮闘勇戦したため、敵軍は総崩れになり総大将以下大半は討ち死にした。

単ページ
-
・1555年、毛利元就は毛利軍は海戦に弱いので厳島を押さえると陶晴賢側の勝利間違いなしとの噂を流し、また、宮島で宮之城を築き兵500を駐屯させた。
この噂に陶晴賢が乗り、岩国、今津室の木から軍船500に分乗した兵20000が宮島に渡った。毛利隊は次の三軍である
(1)主力の第一軍は、地御前の陣地を出て宮島の鼓カ浦に上陸し、博打尾の険を登り背後から陶晴賢軍を襲う

単ページ
-
(2)第二軍は宮島大鳥居付近に上陸し、宮之城を守備する兵と協力して陶晴賢側軍を攻撃する
(3)第三軍は軍船320〜330隻であり、宮島の対岸を警備しつつ陶の水軍と交戦する。

単ページ
-
早朝、毛利元就軍の鬨の声を合図に、吉川元治軍は大鳥居付近に上陸した小早川隆景軍と呼応して陶晴賢の本陣に突入した。
村上武吉の水軍は一気に陶晴賢の水軍に襲い掛かり大半を沈めた。僅かの船が和木や室の木に戻った。

単ページ
-
吉川元春は弘中隆兼父子に遭遇し撃退した。このとき残兵が民家に火を放ったので神殿が消失しない様に鎮火させた。
この隙に弘中隆兼父子は尾根に向かって逃げていったが、包囲され自刃した。陶晴賢は宮島山中深く、嶺付近の高安原まで逃れていた。
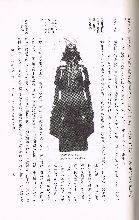
単ページ
-
陶晴賢は船を探すため三浦房清を青海苔浦に派遣したが、吉川家の二宮杢助に見つかり殺害され、
進退窮まった陶晴賢は従者と共に自害した。毛利元就は亡骸をすべて対岸の大野に運び弔った。また社殿を清掃して参拝し、神楽を奉納した。
陶晴賢の首は大野の洞雲寺に埋葬し、陶軍の拠点となった岩国横山の永興寺に本営を移した。

単ページ
-
第二節 元春の防・長両国攻略における間接的な援助
玖珂町の蓮華山城の椙杜隆康は降参したが、鞍掛山城の杉隆泰は大内義長に内応して抵抗する動きを見せた。
そこで、毛利元就・隆元は河内方面から、吉川元春は御庄方面から鞍掛城を攻めたて約1000名の将兵と杉隆泰を討ち取った。
・1556年、玖珂郡の一揆・土豪を掃討し玖珂郡は毛利氏の領有地になった。
大内攻めに備えて,尼子・大友の動きを監視する体制を作った。
・1557年、須々万沼城、富田若山城を攻め落とし、本営を防府松崎の大専坊に移した。

単ページ
-
山口市高城主内藤隆世は、城の守備は困難と考え大内義長を奉じて豊後に渡ろうとしたが、小早川の水軍に妨げられたので
長府の且山城に落ち延びた。しかし、この城は毛利軍の福原貞俊・阿曾沼広秀等の兵が攻撃しており、内藤隆世・大内義長とも自害した。

単ページ
-
第三節 元春の石見における活動
応仁の乱以降、石見国内は大小多くの豪族が各地に割拠していた。
吉見正頼は毛利元就と友好関係を結んでいたので、吉川元治は吉美と協力して尼子軍の動きを抑えることになった。

単ページ
-
・1558年、石見の出羽に駐屯したが尼子側将兵と激戦になり尼子側を壊滅した。毛利f軍と合流した後、12000の大軍で温湯城包囲と
その支城の攻略を始めたたが、尼子の援軍は江の川の洪水で進軍が阻まれ城内は食料が尽き陥落した

単ページ
-
当時、大森銀山からは良質の銀が多量に産出するので尼子・吉川で奪い合いになっていた。
・1558年、銀山城を守備していた吉川軍に対して尼子軍は糧秣運搬通路を遮断し、かつ銀山城に猛攻を加えたので忍原で合戦になった。
元春軍は大敗し、城内の将兵は自刃して銀山城は陥落し、再び尼子側のものになった。

単ページ
-
・1561年、毛利氏に一旦降伏した福屋隆兼は、福光城を襲撃して敗北している。毛利・吉川・小早川軍は福屋一族をことごとく掃討した。
・1561年、銀山城の守備を任された本城常光は一度は毛利の家臣になったが、誠意が疑われ一族すべてが滅ぼされた。
その後、銀山城は毛利家家臣の山元忠によって守備され、永く毛利氏の領有となった。
第四節 元春の出雲における活動

単ページ
-
将軍足利義輝は毛利・尼子の講和を策し、毛利氏の勢力によって将軍の権力を復興せんとしたが、毛利元就は出雲の尼子攻めが先と考えていた。
・1562年、毛利・吉川・小早川軍は出雲・赤穴に駐屯して諸豪族の動きを見ていた。主な豪族が降伏してきたので本軍を松江市の洗骸(あらわい)に移し、
富田月山城を包囲する体制を整えた

単ページ
-
毛利軍が出雲に釘付けになってる隙に、豊後の大友義鎮は豊前の松山城を攻めた
・1562年、毛利隆元は3000の兵で急ぎ松山城の救済に向かったが、毛利元就は将軍足利義輝、岩国永興寺の住職を通じて
和解工作を行い和議が成立した。防府滞在中に和議成立を知った毛利隆元は出雲に帰陣途中、備後の和智城に立ち寄ったが、
和智誠春の居館で饗応を受けた深夜、容態が悪化して死亡した。
・1562年、弔い合戦のため元春は白鹿城を急襲した。尼子倫久の兵1万が白鹿城の援軍にきたが、毛利・吉川・小早川が猛攻を加え、
尼子軍は総崩れとなり敗走した

単ページ
-
白鹿城は援軍の希望がなくなり水・兵糧が欠乏したため約70日間の籠城の末、降伏した。
尼子氏が籠城する富田城への補給は因幡方面から来ていたので、海上封鎖と城塁を暫時攻略して勢力を減退させた。
・1565年、元就は全軍を三分し、三道から総攻撃を決行した

単ページ
-
第一軍は毛利輝元で月山城の西口から、第二軍は吉川元春・元長は月山城の南、塩谷口から、第三軍は小早川隆景が
月山城の北、菅谷口から猛攻を加えた。

単ページ
-
包囲網を強化したため城内兵士の志気は衰え、諸将が次々に毛利軍に降参してきた。
尼子義久兄弟も降伏した。尼子義久兄弟を安芸国高田郡長田の円明寺に監禁した。

単ページ
-
1567年、元就、小早川隆景は安芸の吉田に帰ったが、吉川元春は出雲に滞陣して尼子氏残党の掃討と住民の鎮撫に従事する事になった。

単ページ
-
吉川元春は洗骸滞陣中に、太平記40巻を自筆で写本している。
第五節 元春の新庄凱旋と火野山城の修築

単ページ
-

単ページ
-
第四章 元春の四国・九州方面における活動と山口動乱の鎮定
第一節 元春の四国・九州出征
当時、四国は群雄割拠で互いに争っていた。
・1568年、土佐の長曾我部元親が突然、伊予の河野氏領内に攻め込んできた。厳島の戦では河野氏の水軍に助けられたので、河野氏の援助要請に
応えて毛利・小早川の軍を派遣し、総勢7000の兵は伊予1国を征服した。

単ページ
-
豊後の大友義鎮は、毛利との和議にも拘らず豊・筑方面に侵略してきたので秋月種実の援助要請に応じて九州に出兵する事になった。
・1569年、筑前の立花城は大友軍に奪われれていたため、海陸両面から総攻撃を仕掛けた。また大友軍の援軍に備えて防衛陣地を構築した

単ページ
-
大友援軍との戦闘は激烈を極めたが、吉川元春父子、小早川隆景等の奮戦により大友軍の陣形が崩れ敗走した。
糧秣補給の途が途絶えたため籠城兵の士気が低下して降伏してきた。
一方、尼子の残党である山中幸盛・立原久綱は京都で尼子勝久を擁立して織田信長の援助を受けて出雲に乱入してきた。
また大内家の残党である大内輝弘は大友義鎮の後援を受けて山口に侵入してきた。

単ページ
-
吉川元春・小早川隆景は急遽、筑前立花城を撤退して長府の本陣に帰着した。
その後、大友氏の勢力は拡大し、九州における毛利勢は絶滅に瀕し、立花城に残した及美宗勝・坂元祐・桂元重のみとなった。
補給もなく孤立無援の立花城の将兵は大友氏の説得に応じて開城し、長府本陣まで帰還できた

単ページ
-
第二節 元春の山口動乱の鎮定
大友義鎮は将軍義昭の和議工作に反対し、かつ尼子勝久に毛利領内の攪乱を企てさせ、豊後に滞在中の大内輝弘を
勧説して将兵2000を与え周防に上陸させ、山口に乱入して各所に火を放ち高嶺城を攻略しようとした。
吉川元春は長府の本陣を兵10000と共に出発して船木に着陣すると大内輝弘将兵の志気は極度に落ち、山口を出奔して
豊後に逃亡しようとしたが、船が無く三田尻に到着した。

単ページ
-
吉川元春は残党を殲滅しつつ大内輝弘の軍を富海の浮野峠で粉砕し、退路を断ったので大内輝弘は自害した。

単ページ
-
第五章 尼子勝久の出雲乱入と元春の雲・伯・因・但諸国の経略
第一節 勝久の出雲乱入と元春の雲・伯両国の経略
尼子の残党は諸国を放浪していたが、毛利・吉川・小早川が九州で大友と交戦し山陰地方が手薄になった時、
当時京都東福寺の僧であった尼子誠久の第四子を還俗させ、孫四郎勝久と名乗らせた。当初残党200名であったが、
出雲に上陸して各地に檄を発すると約3000が馳せ参じてきた。勝久はこの兵で富田城を包囲して攻略せんとした

単ページ
-
1570年、毛利輝元、吉川元春、小早川の援軍は出雲に出陣した。
尼子側の山中幸盛、立原久綱は蒼然6700で布部に布陣して、この地で激戦が行われた。
毛利軍は東口、吉川・小早川軍は西口、諸豪族は側面から攻め立てたので尼子軍は大敗を蒙り総退却した。
尼子軍惨敗の結果、富田城の包囲は自ら解かれた。

単ページ
-
毛利元就は安芸の吉田城で大病を患ったので、吉川元春を出雲に残して吉田に引きあげた。
1571年、吉川元春は6000の兵で出雲国内の尼子勢を討伐した

単ページ
-
尼子勝久は隠岐に逃れ、更に京都に走り山中幸盛らの残党と再起の機会到来を待っていた
第二節 元春の因・但両国の経略
・1573年、尼子勝久が出雲乱入したとき、これを援助した因幡の守護山名氏を討伐するため、吉川元春は将兵7000を統率して
因幡に駐屯したところ山名等は次々に降参してきた。

単ページ
-
・1573年、山中幸盛は再度、勝久を奉じて残党3000を集め因幡に侵攻し、山名豊国の居城鳥取城を拠点にした。
吉川元春襲来の風聞が流れると、鳥取城を退城した
・1575年、吉川元春は諸豪族の兵をまとめ15000で因幡に侵攻して平定した。尼子の勢力は殆ど一掃され山中幸盛、勝久は丹波に出奔した。

単ページ
 目次
目次 prev
prev next
next HOME
HOME